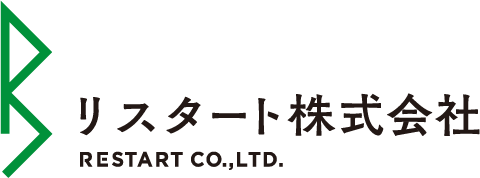税金を滞納し続けるとどうなる?財産を差し押さえられたらどうすればよい?

目次
「税金を滞納するとどうなるの?」
「ひどい取り立てに遭ったりするのかな?」
今すぐ税金を支払える見込みがない場合、このような不安を抱える人もいるのではないでしょうか。税金を滞納し続けると、取り返しのつかないことになるリスクがありますが、回避策もあります。
本記事では、税金の未納を続けた場合のペナルティや、差し押さえから財産を守る方法について解説します。また、納税を先送りにしてもらえる制度も紹介するため、税金を払えそうになくて困っている人はぜひ参考にしてみてください。
税金の未納が続くとどうなる?

税金未払いの状態が続くと、国税庁などの公的機関や債権者によって、さまざまな対応がとられます。最悪の場合、強制執行によって財産が差し押さえられてしまうため、早急かつ誠実に対処しましょう。
以下の見出しでは、税金を滞納したらどうなるか詳しく解説します。
そもそもいつから滞納扱いとなるか
まず「滞納」の定義ですが、これは納期限を1日でも過ぎた時点で該当します。ただし以下3種類の税金については、決算から2ヶ月を過ぎた日から滞納扱いとなります。
● 法人税
● 法人住民税
● 消費税
税金を滞納した場合、さまざまなペナルティが課せられるため要注意です。
税金に延滞税が上乗せされる
納期源までに税金を払わなかったら、さらに延滞税が上乗せされ、負担が大きくなります。
所得税や相続税などの国税は納期限から2ヶ月、市民税や固定資産税などの地方税は納期限から1ヶ月経過すると、延滞税率はより上がってしまいます。したがって、税金を滞納した場合でもなるべく早急に納税したほうがよいです。
納期限後50日以内に督促状が送られてくる
督促状とは、税金未納者に対して差し押さえ前に送られる書類です。税金の納期限を過ぎたまま放置していると、納期限後50日以内に税務署から督促状が送られてきます。地方税の場合は、納期限後20日以内に地方自治体から届きます。
督促状が届いても税金を納めない場合、財産の差し押さえが実行される可能性があります。法律上は、督促状送付から10日経過後より差し押さえが認められているため、残された期間は長くありません。また「督促状が届いてから10日経過後」でない点に注意してください。
ちなみに、税金の納期限から50日を経過しても督促状は届かないことがあります。しかし督促状が送られてこなくても、当然納税の義務は負い続けたままで、かつ50日経過後に届いた督促状も有効です。
電話・文書・訪問により支払い督促が来る
督促状が送付されても納税しないままでいると、電話や文書にて改めて督促が来ます。また、なかには自宅などへ直接職員が訪問してくるケースもあります。
滞納者や保有財産の調査が実施される
支払い督促を無視し続けていると、差し押さえ実行に向けて、滞納者自身の情報や保有財産が調査されます。調査対象は、おもに以下のとおりです。
● 給与
● 預貯金
● 不動産
● 自動車
● 貴金属
● 電化製品
● 生命保険
● 家族構成
● 勤務先
● 取引先
● 戸籍
ちなみに、財産調査は国税徴収法に定められた権限であるため、個人情報保護法には抵触しません。よって、滞納者の同意なく強制的に実施されます。また、財産調査によって給与が差し押さえ対象とされた場合、会社へ「債権差押通知書」が届くため滞納の事実を知られてしまいます。
財産を差し押さえられて強制的に公売にかけられる
督促に応じず税金未納のままでいると、裁判所によって強制実行の判決が下され、財産は差し押さえられます。
差し押さえ対象となった財産は、強制的に公売にかけられ、その売却益は税金未納分に充当されます。例えば自宅が差し押さえられた場合、公売によって買主がついたら強制退去させられます。
そして差し押さえを受けた財産は、その後自身での処分ができません。そのため、自宅が競売にかけられる前に自身で売却することもできなくなります。差し押さえを解除するためには、原則未納分の税金を完納するしかありません。
差し押さえ執行者は、国税の場合は税務署員、地方税の場合は自治体職員です。どちらにせよ法律にて「自力執行権」という強い権限を付与されているため、突然滞納者の家などに訪問し、その場で財産を差し押さえることができます。正当な行政処分であるため、当然拒否はできません。
差し押さえが禁止されているもの
強制執行がされる場合でも、すべての財産が差し押さえられるわけではありません。なぜなら、差し押さえてしまうと生活できないような財産もあるためです。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
● 最低限の衣服や寝具、家具など
● 生活に必要な食料や燃料(3ヶ月分が目安)
● 収入を得るために必要な道具
● 生活に最低限必要な財産(99万円までの現金など)
公売のデメリット
差し押さえによる不動産の公売には、おもに3つのデメリットがあります。
● 市場相場よりも安い価格(7~8割程度)で落札される傾向がある
● 売却のタイミングを自身で決められない
● 買手が着いたら強制退去させられる
ただし強制退去については、差し押さえ後すぐにさせられるわけではありません。公売の場合、通常買手がつくまでに半年~1年程度かかるためです。そのため、その期間内に新居を見つけることになります。
税金滞納による財産差し押さえを防ぐ方法

税金滞納による最大の問題は、財産差し押さえです。以下の見出しでは、差し押さえを防ぐ方法を解説します。
督促状が届いたら税務署に相談する
督促状が届き、かつすぐに納税するのが難しい場合は、まず税務署や地方自治体に相談しましょう。
一番やってはいけないのが、督促の無視です。督促を無視していると、最短10日程度で財産が差し押さえられてしまいます。
一方税務署に相談することで、分割納付や猶予制度によって、一時的に経済難をしのげる可能性があります。以下の見出しでは、それぞれの救済制度について解説します。
分割納付を選択できる場合
税金は一括納付が原則です。しかし滞納者の状況によっては、税務署や地方時自体は一括での支払いを強要せず、分割払いに応じてくれることがあります。
分割払いの場合、本来の期日を過ぎての納税となるため、延滞税は上乗せされてしまいます。とはいえ、一時的な負担を大きく軽減できるため、支払いが困難な場合は相談してみましょう。
猶予制度を利用できる場合
猶予制度は、税金の分割納付すら困難な滞納者に対して、一定の納税猶予期間を与えるものです。猶予制度には、大きく「徴収の猶予」と「換価の猶予」の2種類があります。
徴収の猶予とは、以下の事情に該当する要因によって困窮している場合に、徴収猶予が認められた1年以内の期間について延滞金の全部または一部が免除されるものです。
● 災害や盗難
● 納税者本人または家族の病気、負傷
● 事業の廃止・休止
● 事業についての著しい損失
● 本来の期限から1年以上経過後に、修正申告などによって納付税額が確定した場合
一方換価の猶予とは、一括納税すると生活の維持が困難となるという事情がある場合に、1年以内の期間において財産の差し押さえや処分が猶予されるものです。
税金を払えない場合は融資でしのぐ
税金を払えない場合は、融資で一時的にしのぐ方法があります。しかし、すでに差し押さえが実行されている場合、融資を受けるのは難しいです。
なぜなら金融機関や貸金業者は、審査の際に申込者が納税を期日通りに行っているかまで確認し、滞納者は返済不能のリスクが高いとみて融資を避けたがるためです。
とはいえ、税金の支払いには資金が必要です。そこで以下の見出しでは、差し押さえ実行後も資金調達できる可能性のある方法を紹介します。
不動産担保ローン
不動産担保ローンは、保有する不動産を担保に資金を借り入れる融資サービスです。融資の可否や金額は不動産の価値によって決まるため、現在の年収や信用情報、差し押さえの有無は問われません。今後の返済計画さえ明確になっていれば、審査に通る可能性は十分にあります。
また不動産担保ローンは、比較的金利が低めです。実際に、ノンバンクの無担保ローンの金利が15.0〜18.0%程度であるのに対して、不動産担保ローンの金利は約4.0~10.0%が相場とされています。そのため、家計を圧迫しないような返済計画も立てやすいです。
不動産の任意売却
任意売却とは、金融機関などの債権者や保証人との合意を得たうえで、自身で不動産を売却することです。
公売と主な違いは、売却のタイミングを選べることや、差し押さえの事実を周りに知られるリスクが低いことなどです。任意売却することで、不動産の売却益を一括で確保できるため、納税に対処しやすくなります。
ただし任意売却を選択するためには、差し押さえを解除しなければなりません。しかし、解除は税務署や地方自治体との話し合いにより、解除費用を払うことで認められる場合があります。
そしてこの解除費用は、任意売却の売却代金で支払っても良いことになっているため、差し押さえ後でも実行できる可能性があります。
リースバック
リースバックとは、持ち家を業者へ売却し、その後賃貸契約を結んで今の家に住み続ける方法です。リースバックの場合は買主を探す手間や時間がかからず、かつ売却益を一括で手に入れられるため、滞納している税金の完済がしやすくなります。
リースバックについては、下記の記事で詳しく解説しているため、気になる人はあわせてご覧ください。
関連記事:リースバックとは?デメリット・メリット・やばいといわれる理由を解説
財産を差し押さえられた際の対処法
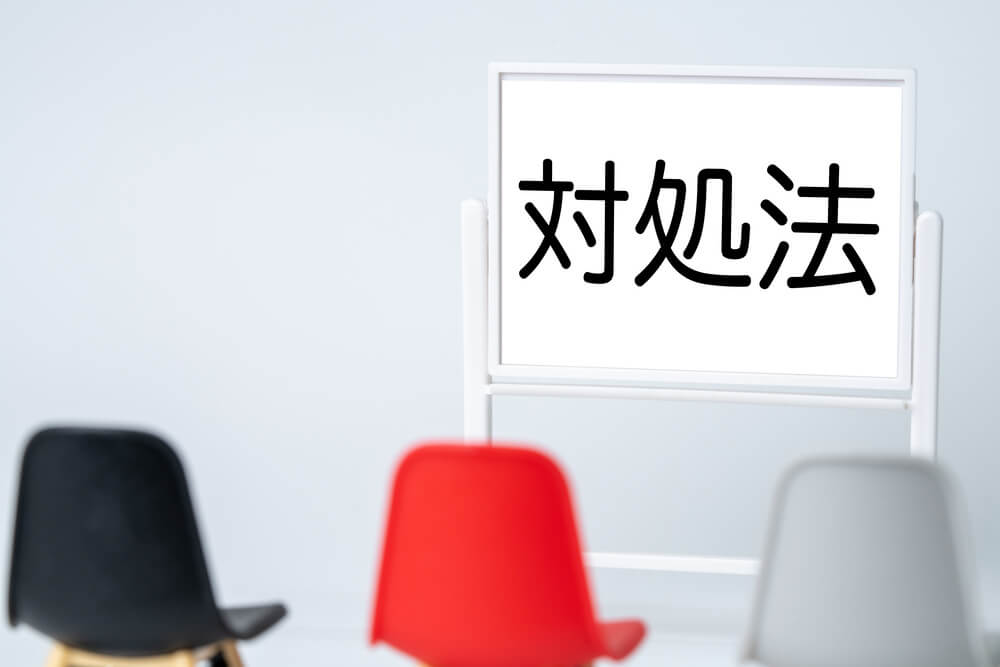
財産を差し押さえられた場合、原則として完納しない限り、差し押さえの解除はされません。ただし、税務署や地方自治体への解除要請によって認められるケースもあります。
まとめ
税金を滞納した場合、延滞税の上乗せや財産差し押さえなどのペナルティが課せられます。特に財産差し押さえによって、日常生活すら危ぶまれる可能性があるため、督促は無視せず税務署や地方自治体に相談するなど適切な対処をしましょう。
また、不動産の場合は任意売却やリースバックによって差し押さえを回避することもできます。
この記事の監修者

リスタート株式会社 代表取締役 峯元 竜
建設業個人事業主を7年経営後、不動産業を12年間経験。2017年の独立開業後、事業の負債を抱えながら働きつつ副業を掛け持ちしていた経験をもとに、依頼者目線で課題解決に取り組む。
任意売却やリースバックを通じて、一人でも多くの依頼者が安心して新しい生活をスタートできるよう支援。また独自のネットワークを活かし、複雑な金融機関との交渉や、迅速な売却サポートにも強みを持つ。