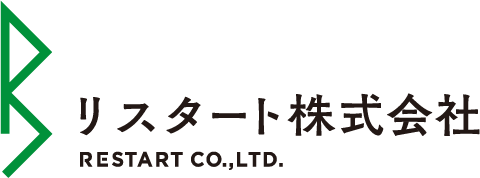住宅ローン返済中の家を売る方法とは?売却方法や注意点を解説

目次
転勤や離婚、住宅ローンの滞納などが原因で、自宅の売却を検討する人もいるでしょう。しかし、いざ売却を検討しても、「住宅ローンの残債がある場合に売却できるの?」、などの疑問を抱く人もいるでしょう。
この記事では、住宅を売却する際に発生するいくつかのケースを取り上げ、スムーズに自宅を売却する方法を解説します。自宅の売却を検討中の人、または将来その可能性がある人は、ぜひこの記事を参考にし、スムーズに売却するための手順を理解しておきましょう。
住宅ローンが残っている物件を売る準備をしよう

住宅ローンが残っている物件を売ると決意した場合、まずは次の3つから取り掛かりましょう。
住宅ローンの残債を確認しておく
売却を決意したら、まずは現在の住宅ローン残債を調べることから始めましょう。
住宅ローンが残っている物件を売却する場合、売却価格によりローン完済が可能か否かを見極めることが重要です。
家を売ってもローンが残るのか、それとも完済できるのかによって、売却手順などの進め方が変わってきます。そのためにもローン残債は事前に把握しておきましょう。
住宅ローンの残債を確認する方法は主に次の3つです。
● 残高証明書を見る
● ネットで確認する
● 窓口で確認する
物件の売却金額を査定してもらう
次に、不動産会社に依頼して、自宅がいくらで売却できそうか査定します。査定額を把握しておくことで、残債が残りそうか、それとも完済できそうかが見極めやすくなるのです。
不動産会社に査定を依頼する場合、1社に限定せずに複数社へお願いすることをおすすめします。複数社に依頼することで、いくらで自宅が売却できそうか平均値を掴めます。また、複数の担当者と会話することで、自身にとってより最適な不動産会社が見つかるでしょう。
売却金額で住宅ローンを完済できるか計算する
次に、「住宅ローンの残債」と「売却価格」を比較し、ローン完済が可能なのか試算します。
この試算結果により、ローン残債と売却価格の関係性に基づき、「オーバーローン」もしくは「アンダーローン」なのかを判断します。
「オーバーローン」とは、ローン残債が売却金額を上回る状況のことです。具体的には、売却後もなお返済するべきローンが残る状況を指します。
一方の「アンダーローン」とは、ローン残債が売却金額を下回り、売却益が発生する状況のことです。これは、売却によりローンを完済でき、更に資金が残る状況を指します。
もし「オーバーローン」となってしまった場合は、後述する対策を取り、それに基づいて売却活動を進めていく必要があります。
住宅ローンが残っている物件の注意点は6つ

住宅ローンが残っている物件を売却する際の注意点は次の6つです。順に解説していきます。
住宅ローン完済と抵当権抹消を行う必要がある
1つ目の注意点は「住宅ローン完済と抵当権抹消を行う必要がある」ことです。
住宅ローンが残っている物件を売却することは可能ですが、そのためには住宅ローンを完済し抵当権を抹消しなければなりません。一般的に抵当権が設定されたままだと、住宅は売却できないのです。
「抵当権」とは、不動産などを「担保」にして、もし返済できなくなった場合に、抵当権を設定している不動産を売却し、その売却で得たお金で返済する権利です。ローン返済が困難になると、融資している金融機関は抵当権の設定をしている不動産を差し押さえます。
その後、裁判所に認められれば対象不動産は競売に掛けられ、強制的に売却させられるのです。
物件の売却には諸費用がかかる
2つ目は「売却には諸費用が発生する」ことです。
意外と見落としがちな点ですが、物件を売却する際は主に以下のような諸費用が発生します。
● 仲介手数料
● 登記費用
● 印紙税
● 住宅ローン返済手数料
● 譲渡所得税と住民税(発生しないケースもあり)
これらの諸費用を加味し、売却後の実質的な利益を把握しておくことで、より適切な売却判断が可能となります。
確定申告で所得税の還付があるか確認する
3つ目は「所得税の還付が可能か確認する」ことです。
自宅を売却したことで損失が発生した場合、損失部分を3年間にわたって所得金額から繰り越して控除できます。これにより、他の所得と合算した上で確定申告を行い、払い過ぎた税金の還付を受けられます。
たとえば、Aさんが自宅を売却したことにより100万円の損失が発生したとします。一方で、Aさんの給与所得が500万円であり、その全額に対する税金をすでに支払っていました。この損失と所得を合算すると400万円になります。
よってAさんは500万円に対する税金をすでに支払っているため、確定申告することで、払い過ぎた税金が還付されることになります。
売却の相談・依頼をする不動産会社は慎重に選ぶ
4つ目は「相談・信頼できる不動産会社を選ぶ」ことです。
自宅の売却を進めていく際に、不動産会社が物件の広告活動や価格交渉などを担当します。
不動産会社の能力次第では、売却価格に数百万円の差が生じることもあるのです。
また、相談しやすい不動産会社であれば、トラブルも少なく円滑に売却を進めていけるでしょう。
とくに住み替えの際は、新居の購入と旧居の売却がセットになります。これらのタイミングをうまく調整するためにも、経験と実績が豊富で信頼できる不動産会社の選択が欠かせません。
住み替えなら売り先行を検討する
5つ目は「住み替えなら売り先行を検討する」ことで、「売り先行」は先に今の自宅を売却してから、新居探しを開始することです。
売り先行のメリットは先に自宅を売却するので、売却代金をそのまま新居の購入資金にあてることができ、今後の資金計画が立てやすくなることです。
さらに、二重ローンを避ける観点からも、住み替えの場合は売り先行をおすすめします。
ただし、売り先行の注意点として、住みながら家を売却することになるので、内覧への対応が必要です。そのため、不動産会社を通じて内覧日などのスケジュール調整をしなければなりません。
買い先行の場合はつなぎ融資も検討する
6つ目は「買い先行の場合はつなぎ融資も検討する」ことです。買い先行とは、新居の購入を先、家の売却を後に行うことです。買い先行の場合は、時間をかけて理想の物件を探せられるので、新居に対するこだわりが強い人に向いているでしょう。
ただし、買い先行では新居の購入費用を準備する必要があります。そこで役立つのが「つなぎ融資」です。つなぎ融資は、一時的なローンで、現在の自宅を売却するまでの間だけ融資を受けられます。
つなぎ融資を活用することで、新居の頭金にかかる資金面の負担を軽減できます。自宅を売却できれば、受けたつなぎ融資はすぐに返済できます。
住宅ローンが残っている状態で離婚する場合は?

離婚が原因で自宅の売却を検討している人もいるでしょう。住宅ローンが残っている状態で離婚する場合、次のことに注意が必要です。
残債はローン名義人が離婚後も支払い義務を負う
離婚が原因で自宅の売却を検討している場合でも、住宅ローンの残債は離婚後も名義人が支払い義務を負います。
また、ローン残債が売却価格を上回るオーバーローンの場合は、離婚による住宅ローン残債の折半は原則必要ありません。住宅ローンなどの借金については、資産と判断されず基本的に財産分与の対象にならないと考えられるからです。
離婚後も連帯保証人は変えられない
夫婦どちらかの名義で不動産を購入し、その配偶者が連帯保証人になるケースもよくみられます。この場合、もし離婚をしてもローン残債が残る限り、連帯保証人の解除は原則できません。
住宅ローンを融資している金融機関からすると、名義人の離婚は住宅ローンとは関係ないと判断されるからです。この場合、一括繰り上げ返済で住宅ローンを完済すれば、連帯保証人を解除できますが、現実的に厳しいと感じる人も多いと思います。
そのような状況では、住宅ローンの借り換えを検討してみるのも選択肢の1つです。借り換えに成功すれば、前の金融機関で借りた住宅ローンを全額返済され、連帯保証人は解除されます。
ただし、借り換えの際には諸費用が発生することや、前の住宅ローンよりも条件が悪くなる可能性もあります。そのようなリスクも考慮した上で借り換えを検討しなければなりません。
共同名義の場合は売却手続きが面倒 になる
自宅を夫婦の共同名義で所有している場合、離婚時に夫や妻の同意がなければ、自宅を売却することはできません。そのため、自宅を売却したい場合、まずは名義人の同意を得ることが必須になります。
また、この状況でもオーバーローン、アンダーローンの問題が関わってきます。
オーバーローンの場合は、残債を完済できないと抵当権の解除ができず、自宅の売却ができません。その場合は、不足分を夫婦の資産から補うか、親族から援助をもらうかなどして完済しなければなりません。
アンダーローンの場合は、自宅を売却することに相互とも同意しているのであれば売却し、残った財産は夫婦で分け合います。
オーバーローンの物件を売却したい場合
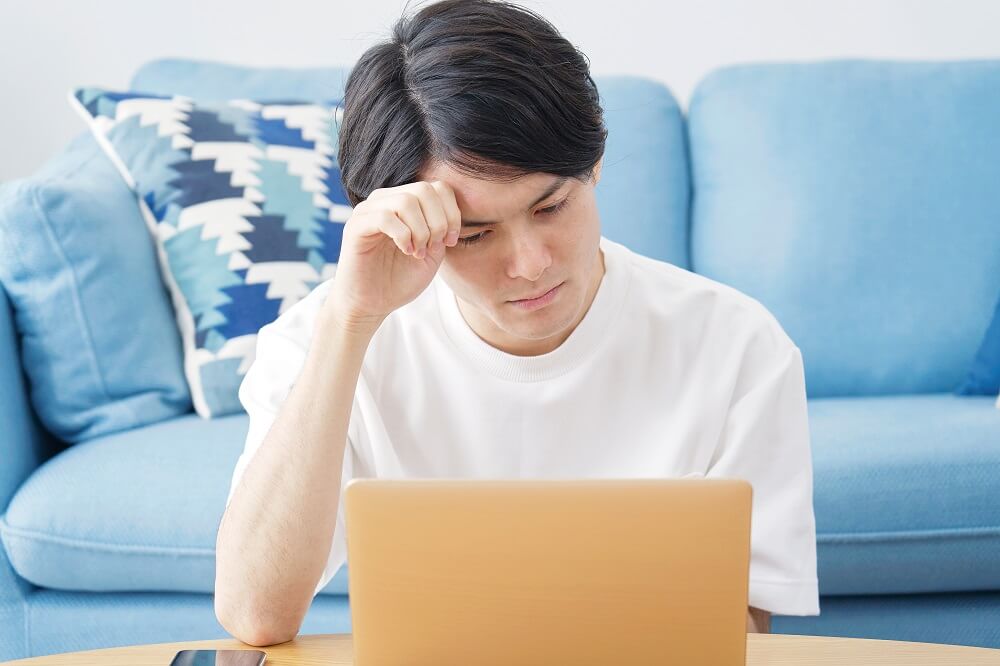
次に、オーバーローンの物件を売却したい場合の解決策として、以下が考えられます。
● 自己資金で足りない金額を補って完済する
● 住み替えローンを活用する
● 無担保ローンを活用する
● 任意売却を検討する
以下では、それぞれについて解説します。
自己資金で足りない金額を補って完済する
1つ目の選択肢として、自己資金でローン残債を補う方法です。自己の預貯金などで足りない部分を補うことがシンプルな解決策です。しかし、自己資金だけで完済することがきびしい人もいるでしょう。
その場合は両親や祖父母などから資金援助をお願いすることも選択肢の1つです。もし、両親や祖父母から援助の話しがあれば、積極的に話し合いを進めてみてもよいでしょう。
住み替えローンを活用する
「住み替えローン」とは、返済しきれなかったローン残債を上乗せして新たにローンを組むことです。
たとえば、住み替えのために自宅を売却する場合、200万円の残債が発生。そして、次に購入する自宅が4000万円だとします。住み替えローンでは、残債である200万円を上乗せした4200万円でローンを組めます。こうすることで、前の自宅のローン残債が無くなり、抵当権の解除ができるのです。
ただし、上乗せすることで借り入れの金額が大きくなるため、ローン審査がきびしくなり、融資を受けられないリスクも生じます。
無担保ローンを活用する
具体的には銀行や消費者金融から借り入れてローンを組み、残債を返済します。
住宅ローンは、借り手の住宅を担保にする条件で融資を行いますが、一方で、無担保ローンの場合は、担保を必要とせずに融資が可能です。
ただし、無担保ローンの場合は借入額に上限が設けられており、残債が大きい場合は無担保ローンだけで完済することは難しいかもしれません。
また、無担保ローンは住宅ローンに比べて金利が割高になり、返済期間も短く設定されているため、毎月の返済負担が増えるリスクも存在します。
任意売却を検討する
「任意売却」とは、住宅ローンの返済が難しい場合に、融資を受けている金融機関の合意を得た上で、自宅を売却する方法です。任意売却に成功すれば、残債を完済できなくても売却できるのです。
通常、住宅ローンの滞納が一定期間続いた場合、融資している金融機関は自宅を差し押さえし、最終的に競売に掛けて売却します。そして、売却して得た資金で返済を行いますが、任意売却を活用すれば、強制的に売却をされず、通常の不動産売却を選択できるのです。
また、任意売却をするには金融機関の許可以外にも、一定期間の滞納や返済不能状態などの条件が設けられており、だれでも活用できるわけではありません。
したがって、任意売却は返済がきびしくなった場合の最終手段となります。なるべく任意売却を活用することなく、売却する方法を選びましょう。
アンダーローンの物件を売却したい場合

ここからは、「アンダーローン」の物件を売却する方法を解説します。
アンダーローンの場合、売却金額でローン残債を完済できます。そのため、売却するにあたって、とくに問題が生じることは少ないでしょう。
ただし、売却には仲介手数料や登記費用などの諸費用が発生します。これらの費用を事前に計算し、売却後にいくら手元に残るのかを把握しておくと、その後の資金計画をスムーズに立てられるでしょう。
住宅ローンを返済中の物件売却は専門家に相談しよう

自宅を売却する場合、不動産会社に相談する人が多いと思いますが、その他にも次のような専門家に相談できます。
|
相談先 |
相談内容 |
|
不動産会社 |
売却査定、広告活動、売却活動、契約書作成 |
|
不動産鑑定士 |
売却査定、不動産鑑定書の作成 |
|
土地家屋調査士 |
土地の境界確定、測量図の作成 |
|
弁護士 |
売却先とのトラブル |
|
司法書士 |
表題登記作成、所有権保存、移転、抵当権設定表記、抵当権抹消登記 |
|
税理士 |
確定申告についてアドバイス |
以下で順に解説していきます。
不動産会社
自宅の売却を検討する際に、まずは不動産会社から相談しましょう。
不動産会社は売却査定から広告活動、売却活動、契約書の作成、引き渡しまで、売却までの全工程についてアドバイスしてくれます。
したがって、良い不動産会社を選べられるかどうかが売却成功の重要な鍵になるでしょう。
不動産会社への相談は無料で対応してくれます。売却に際して発生する費用は仲介手数料で、その金額は物件価格によって異なりますが、(物件価格×3%)+6万円が上限になります。
不動産鑑定士
自宅の売却査定は不動産会社でも実施していますが、より詳しい査定を求める場合は不動産鑑定士に依頼するのも1つの選択肢です。
ただし、特別な事情を抱えていない土地や建物であれば、有料で不動産鑑定士に相談するほどではないかもしれません。そのような場合は不動産会社が実施している無料査定で十分といえるでしょう。
もし、不動産鑑定士に依頼する場合、一般的な住宅であれば20万~30万円が費用相場になります。
土地家屋調査士
土地の売買では境界の確定や測量が重要な要素となります。境界の確定や測量ついては、専門の土地家屋調査士に相談するのが最適です。
土地においては境界トラブルが多く、土地の売買を行う際は、境界をきちんと確定しておくことが重要になるからです。
もし、売却時に境界がはっきりしていない場合は土地家屋調査士に依頼して、事前に問題を取り除いておくとよいでしょう。
境界確定測量に必要な費用の相場は土地の面積や、調査会社によって異なります。そのため、境界確定測量が必要になった場合は、土地家屋調査士に確認することをおすすめします。
弁護士
売却において法律的なトラブルが生じている場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。代理人として代わりに話をしてくれることもあります。
弁護士費用はかかりますが、法律に関するトラブルは法律の専門家である弁護士を活用し、早期に問題を解決することで、結果的に時間やコストの節約につながります。
相談料は1回あたり5,000円以上が相場といわれています。具体的な費用は弁護士やその事務所により異なるため、直接相談して確認しましょう。
司法書士
不動産の表題登記作成や所有権保存、移転、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などは自身でも法務局で申請できますが、手続きが複雑なため司法書士への依頼が一般的です。
司法書士へお願いする場合の費用は4万5,000円~6万5,000円が相場といわれています。
税理士
もし自宅を売却して、利益が発生した場合は確定申告が必要になります。自身で確定申告することに不安を感じる人も多いでしょう。
そのような場合は税理士への相談が有効です。税理士にお願いすれば、確定申告書の作成について的確なアドバイスを提供してくれます。
通常、税理士に依頼する場合は相談料や確定申告書の作成費用が発生します。しかし、各地域の自治体などが無料相談を実施していることもあるので、そちらを利用して確定申告書を作成するのも1つの選択肢となるでしょう。
まとめ
住宅ローン返済中の家を売却する場合、まずはローン残債を確認することです。そして家の売却金額の査定を行いオーバーローンになるかアンダーローンになるかを把握しましょう。
オーバーローンの状態であれば、自己資金で不足額を補うか、住み替えローンや無担保ローンを活用してローン完済をします。
住み替えの目的で売却する人は、売り先行で進めていくと資金計画を立てやすくなります。
また、自宅を売却した場合に利益が発生すると、その翌年に確定申告が必要になるので忘れずに行いましょう。1人で申告書を作成するのが不安な人は税理士に相談するのも選択肢の1つです。
このように、家を売却するには多くの工程を踏んでいく必要があります。この工程をスムーズに進めていくためには、不動産会社選びが重要な鍵になります。優秀な不動産会社を選ぶことで、ストレスを軽減するだけでなく、売却価格にもプラスの影響を与えるでしょう。
そのためにも、複数社に査定を依頼し、自身にとって最適な不動産会社を見つけてください。
この記事の監修者

リスタート株式会社 代表取締役 峯元 竜
建設業個人事業主を7年経営後、不動産業を12年間経験。2017年の独立開業後、事業の負債を抱えながら働きつつ副業を掛け持ちしていた経験をもとに、依頼者目線で課題解決に取り組む。
任意売却やリースバックを通じて、一人でも多くの依頼者が安心して新しい生活をスタートできるよう支援。また独自のネットワークを活かし、複雑な金融機関との交渉や、迅速な売却サポートにも強みを持つ。