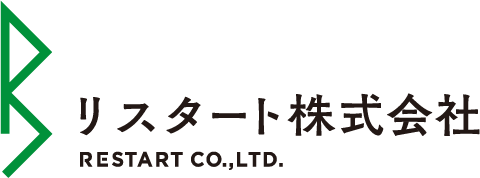共有名義の不動産は売却できる!共有名義の家を売る方法やトラブルの対処法
共有名義の不動産をお持ちの方、売却にお悩みではありませんか。共有名義だと売却には制限があり、トラブルも起こりやすいと思われがちですが、実は売却する方法はいくつかあります。
共有者全員の合意を得る方法、自分の持分のみを売却する方法など、状況に合わせて選択できます。このコラムでは、そんな共有名義の不動産売却の具体的な方法から、発生しやすいトラブルの対処法まで詳しく解説しています。
目次
-
-
-
1.共有名義とは
1-1.共有持分の不動産なら自由に売却できる
1-2.共有名義の不動産を売却する方法
2-1.不動産全体を共有者全員の同意を得て売却する
2-2.自分の持分を他の共有者に売却する
2-3.自分の持分を共有持分買取業者に売却する
2-4.分筆して売却する(土地の場合)
3-1.共有名義の不動産売却で注意すべきトラブル
3-2.無断で売却することによる関係の悪化
3-3.共有物分割請求訴訟への発展
3-4.共有持分買取業者への売却によるリスクの発生
4-1.共有名義の不動産売却で押さえるべきポイント
4-2.共有者を明確にする
4-3.共有者の調整役を決める
4-4.税金などの費用負担割合を決めておく
4-5.最低売却価格を設定する
4-6.確定申告を忘れずに行う
5.共有名義の不動産売却は専門家に相談を
-
-
共有名義とは

共有名義の不動産とは、ひとつの不動産を複数人で、共同で所有している状態を指します。各共有者には、その不動産に対して持分という割合的な権利が認められています。
不動産が共有名義になるケースとしては主に以下のようなものが挙げられます。
l 相続により、被相続人の所有していた不動産を複数の相続人で受け継いだ場合
l 親子などで二世帯住宅を建築し、土地や建物を共同で所有する場合
l 夫婦でマイホームを購入し、共同名義で登記した場合
これらのように、共有名義はいくつかの典型的なケースで発生します。共有名義の不動産における、それぞれの共有者の権利範囲と主な行為は下記になります。
|
範囲 |
主な行為 |
|
単独で可能な行為 |
各共有者の持分の処分、使用、保存行為(修繕等) |
|
過半数の同意が必要な行為 |
共有物の管理行為(賃貸借等) |
|
全員の同意が必要な行為 |
共有物の変更・処分行為(増改築、売却等) |
このように共有名義の不動産では、権利範囲に応じて単独や一部の同意で進められる行為と、全員の合意が必要な行為に分けられます。とくに不動産全体を売却する場合は、変更・処分行為に該当するため、共有者全員の同意が必須となる点に注意が必要です。
共有持分の不動産なら自由に売却できる

共有持分とは、共有名義の不動産(複数人が名義人となっている不動産)において、各共有者が持つ所有権の割合のことを指します。例えば夫婦でマンションを共有名義で所有している場合、夫と妻はそれぞれが共有者であり、一定の共有持分を有しています。
共有名義の不動産は、共有者全員の合意がないと売却できないのが原則ですが、各共有者は自分の共有持分だけであれば、他の共有者の同意なしに自由に売却することができます。つまり共有者は、不動産全体に対しては不完全な権利しか持っていませんが、自身の共有持分に対しては完全な権利が認められているのです。
例えば、兄弟2人でアパートを相続して共有名義になっているケースで、弟が2分の1の共有持分を有しているとします。この場合、弟は自身の2分の1の共有持分を、兄の承諾を得ることなく第三者へ売却することが可能です。持分の売却については他の共有者への同意や通知は不要であり、弟の自由な判断で売却を進められるのです。
ただし一般的に共有持分のみの売却は、購入者が見つかりづらく、また持分割合に応じた価格にしかならないデメリットもあります。とはいえ資金が必要な場合など、共有持分の売却は共有者個人の裁量で選択できる有効な方法の一つといえるでしょう。
共有名義の不動産を売却する方法

共有名義の不動産を売却する際には、以下の方法があります。
l 不動産全体を共有者全員の同意を得て売却する
l 自分の持分を他の共有者に売却する
l 自分の持分を買取業者に売却する
l 分筆して売却する(土地の場合)
それぞれの方法について、具体的な流れや注意点を説明します。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った売却方法を選ぶことが大切です。
不動産全体を共有者全員の同意を得て売却する
共有名義の不動産を売却する場合、全体を売却するためには、すべての共有者の同意が必要です。これは、不動産全体の所有権を一括して第三者に移転するために、全員が売却に合意する必要があるからです。この同意は、口頭ではなく書面で明確にすることが望ましいです。
【売却の流れ】
1. 共有者間の合意形成
まず、すべての共有者が不動産の売却に合意する必要があります。この合意を得るためには、共有者間での話し合いが不可欠。共有者全員が納得する価格や条件を決定します。
2. 不動産会社への相談
合意が得られたら、不動産会社に売却の相談を行います。不動産会社は、売却のサポートを行い、市場価格の査定や販売戦略の提案を行います。
3. 売却活動
不動産会社が売却活動を行います。広告を出したり、見学会を開いたりして、買い手を探します。
4. 売買契約の締結
買い手が見つかったら、売買契約を締結します。この際、共有者全員が契約書に署名・捺印する必要があります。
5. 所有権移転手続き
売買契約が締結されたら、所有権の移転手続きを行います。これは、法務局での登記手続きとなります。
【共有名義の不動産売却に必要な書類】
l 登記済権利証または登記識別情報通知書
不動産の所有権を証明する書類です。これは、売却の際に所有者であることを証明するために必要です。
l 身分証明書
共有者全員の身分証明書が必要です。これは、本人確認のために使用されます。
l 印鑑証明書
共有者全員の印鑑証明書も必要です。売買契約書に押印する実印の証明として使用されます。
l 住民票
共有者全員の住民票も必要です。これは、共有者の現在の住所を証明するために使用されます。
【注意点】
l 共有者全員の同意が必須
一人でも反対する共有者がいる場合、全体の売却はできません。そのため、事前にしっかりとした話し合いと合意形成が重要です。
l 手続きの複雑さ
共有者が多い場合、それぞれの署名や捺印が必要となり、手続きが複雑になることがあります。また、共有者が遠方に住んでいる場合は、委任状を用意する必要があるかもしれません。
l 専門家のサポート
手続きが複雑な場合は、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。彼らは法的な手続きをスムーズに進めるための助言をしてくれます。
自分の持分を他の共有者に売却する
共有名義の不動産のうち、自分の持分だけを他の共有者に売却する方法もあります。この場合、他の共有者の同意は不要で、自分の判断で売却できます。
まず、売却したい持分の価格を算出し、他の共有者に買取を打診します。合意に至れば、売買契約書を作成し、代金の受け渡しを行います。最後に、持分移転の登記をすれば完了です。
ただし、あまりにも安価で売却すると、売却ではなく贈与とみなされ、税務上の問題が生じる可能性があります。適正価格での売却を心がけましょう。また、譲渡所得税や登録免許税などの税金も発生するので、事前に調べておく必要があります。
自分の持分を共有持分買取業者に売却する
自分の共有持分を売却したいものの、他の共有者が買い取ってくれない場合は、共有持分買取業者に売却するという選択肢もあります。共有持分買取業者は、共有持分のみの買取を専門に行う業者です。
持分を売却したい旨を買取業者に伝え、査定を依頼します。条件が合えば売買契約を結び、法務局で持分移転登記を行えば完了です。他の共有者の同意は不要で、比較的スピーディーに売却できるのがメリットです。
ただし、共有持分は単独所有権に比べて著しく価値が下がるため、大幅な買い叩きになる可能性が高いことには注意が必要です。また、買取業者が他の共有者に売却を持ちかける場合もあり、関係性が悪化するリスクもあります。
H3.分筆して売却する(土地の場合)
土地の共有名義の場合、分筆して売却する方法もあります。分筆とは、一つの土地を複数に分け、それぞれを単独名義にすることです。
まず、専門家に依頼して土地の測量を行います。測量結果に基づいて分筆登記を行い、それぞれの土地を単独名義にします。分筆後は、各自で土地を自由に売却することができます。
ただし、土地の広さや形状によっては、等分に分筆できないケースもあります。また、有効な宅地として分筆できるかどうかの調査も必要。分筆にかかる費用も負担しなければならないので、売却益とのバランスを考える必要があるでしょう。
共有名義の不動産売却で注意すべきトラブル

共有名義の不動産を売却する際には、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
l 無断で売却することによる関係の悪化
l 共有物分割請求訴訟への発展
l 共有物分買取業者への売却によるリスクの発生
ここでは、上記の主なトラブルの種類とその対処法について詳しく説明します。
無断で売却することによる関係の悪化
共有名義の不動産を無断で売却することは、共有者間の関係を著しく悪化させる原因となります。たとえば、一人の共有者が他の共有者に断りなく自分の持分を売却した場合、残された共有者は突然新しい共有者と共同所有することになります。
これにより、信頼関係が崩れ、最悪の場合、長期間の法的紛争に発展する可能性があります。このような事態を避けるためには、売却を検討する際には事前に全ての共有者と十分に話し合い、合意を得ることが重要です。
共有物分割請求訴訟への発展
共有名義の不動産を巡るトラブルが深刻化すると、共有物分割請求訴訟に発展することがあります。これは、共有者間での合意が得られない場合に、裁判所に対して不動産の分割または売却を求める訴訟です。
訴訟に発展すると、時間と費用がかかるだけでなく、最終的な判決により不動産の強制売却や代償金の支払いが命じられることがあります。このようなリスクを避けるためには、共有者間での早期の合意形成が重要です。
共有物分買取業者への売却によるリスクの発生
共有名義の不動産を共有物分買取業者に売却する場合、いくつかのリスクが伴います。まず、買取業者は共有持分を安価で買い取り、最終的には全ての持分を手に入れて高値で売却することを目的としています。その過程で、他の共有者に対して強引に売却を迫ることがあり、これが新たなトラブルの原因となります。
また、買取業者との共有状態が続くことで、不動産の利用や管理に関しても多くの制約が生じます。このようなリスクを避けるためには、できるだけ他の共有者と協力して売却を進めることが望ましいです。
共有名義の不動産売却で押さえるべきポイント

共有名義の不動産を売却する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。これらのポイントを理解し、適切に対処することで、スムーズな売却とトラブルの回避が可能になります。
l 共有者を明確にする
l 共有者の調整役を決める
l 費用負担割合を決めておく
l 最低売却価格を設定する
l 確定申告を忘れずに行う
以下で、具体的な方法と注意点について説明します。
共有者を明確にする
共有名義の不動産を売却する前に、まず共有者を明確にすることが重要です。不動産の登記簿を確認し、全ての共有者の名前と持分を把握します。共有者が複数いる場合、全員の同意が必要になるため、共有者全員と連絡を取り合い、合意を得るための準備を進めます。
また、共有者の所在が不明な場合は、不在者財産管理人制度を利用して、裁判所に代理人を選任してもらうことも検討しましょう。
共有者の調整役を決める
共有名義の不動産を売却する際には、共有者の間で調整役を決めることが重要です。調整役は、共有者全員の意見をまとめ、売却手続きをスムーズに進める役割を担います。調整役を選ぶ際には、信頼できる人を選ぶことが大切。
また、調整役には、法律や不動産取引に関する基本的な知識を持っていることが望ましいです。共有者間のコミュニケーションを円滑にするために、定期的なミーティングを開催し、情報を共有することも重要です。
税金などの費用負担割合を決めておく
共有名義の不動産を売却する際には、税金やその他の費用負担割合を事前に決めておく必要があります。これには、不動産売却に伴う譲渡所得税や登記費用などが含まれます。一般的には、持分割合に応じて費用を負担することが合理的です。
ただし、特殊な事情がある場合は、共有者間で話し合い、適切な負担割合を決めることが大切です。費用負担について事前に合意しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
最低売却価格を設定する
共有名義の不動産を売却する際には、最低売却価格を設定しておくことが重要。最低売却価格を設定することで、共有者全員が納得のいく価格で売却することができます。最低売却価格を設定する際には、不動産の市場価値を正確に把握するために、不動産査定を行うことが必要です。
また、価格交渉が発生した場合でも、最低売却価格が設定されていれば、迅速に判断を下すことができます。
確定申告を忘れずに行う
共有名義の不動産を売却した後は、確定申告を忘れずに行いましょう。不動産の売却益に対しては、譲渡所得税が課税されるため、売却後の所得について正確に申告する必要があります。
確定申告の際には、売却時の契約書や費用明細、取得費用の領収書など、必要な書類を全て揃えておくことが大切です。確定申告を正確に行うことで、税務上のトラブルを避けることができます。
共有名義の不動産売却は専門家に相談を
共有名義の不動産の売却は、単独名義の不動産とは異なり、複数の所有者が関与するため、手続きや調整が非常に複雑です。トラブルを未然に防ぎ、スムーズに売却を進めるためには、専門家への相談が欠かせません。
専門家は、共有者間の意見の調整や法的な手続き、税務対策など、多岐にわたるサポートを提供してくれます。例えば、不動産の共有持分をどのように売却するかについてのアドバイスや、共有者全員の合意を得るための交渉術を教えてくれます。また、売却後の確定申告や税金の手続きについても的確なアドバイスを受けることができます。
リスタート株式会社では、共有名義の不動産売却に関する無料相談も受け付けているので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修者

リスタート株式会社 代表取締役 峯元 竜
建設業個人事業主を7年経営後、不動産業を12年間経験。2017年の独立開業後、事業の負債を抱えながら働きつつ副業を掛け持ちしていた経験をもとに、依頼者目線で課題解決に取り組む。
任意売却やリースバックを通じて、一人でも多くの依頼者が安心して新しい生活をスタートできるよう支援。また独自のネットワークを活かし、複雑な金融機関との交渉や、迅速な売却サポートにも強みを持つ。